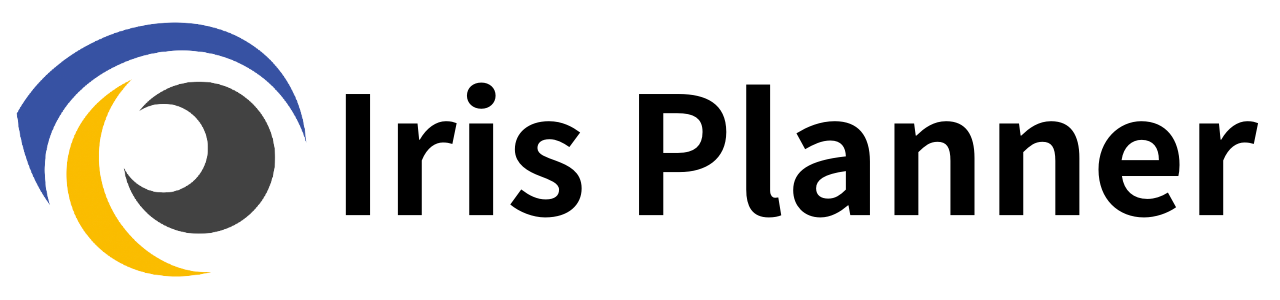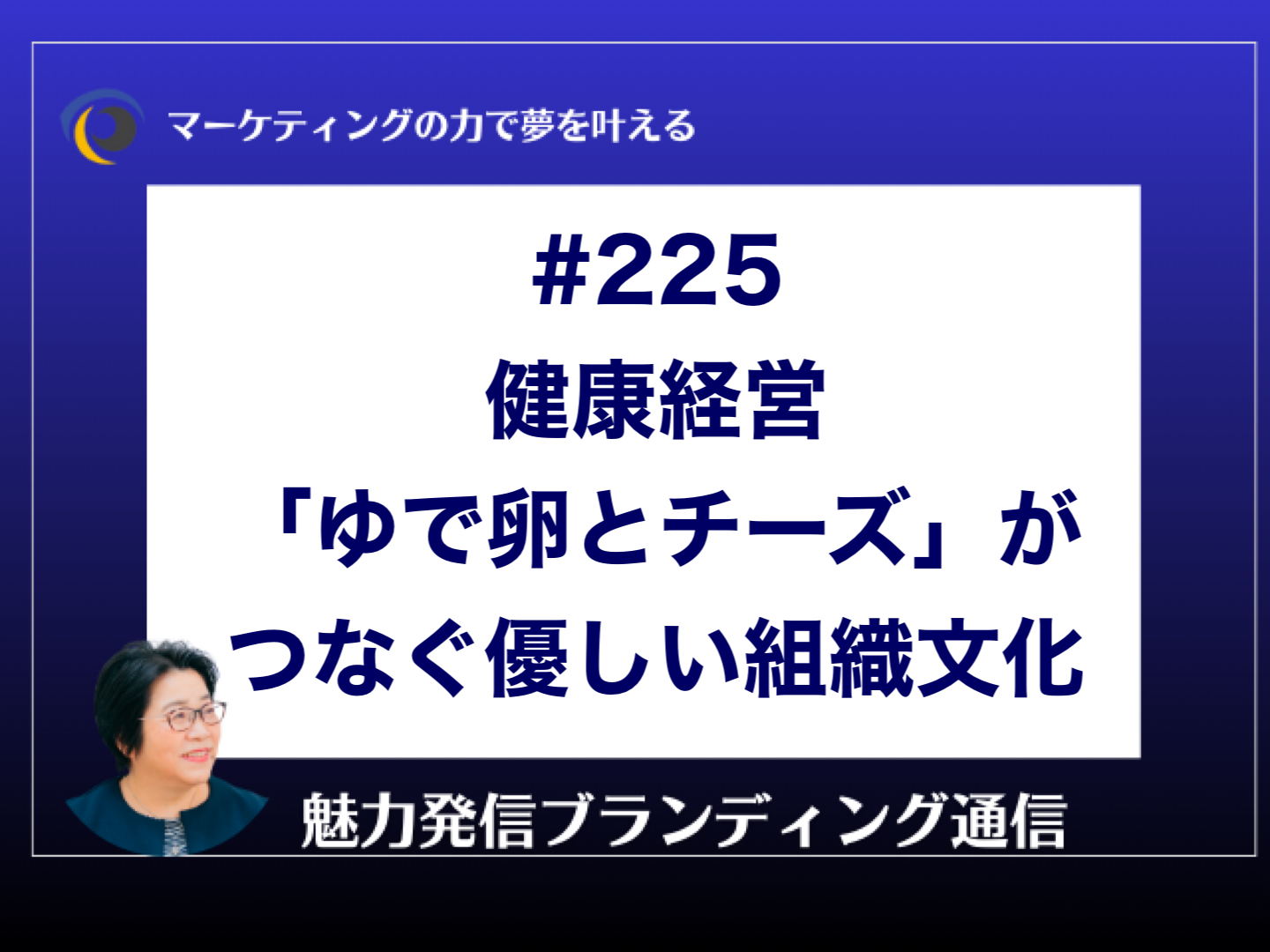先日、青森の「健康経営」セミナーでの
気づきをお伝えしました。
2日目の今日は、健康経営に取り組むことで
「なぜ組織文化が変わるのか?」に焦点を当てます。
私はもともと広報のサポートが専門ですが、
広報と健康経営には共通点が
多いと感じています。
それは、どちらも 「お互いを尊重し、
感謝し合える社風を育てる」 という点です。
🔸広報と健康経営に共通するもの
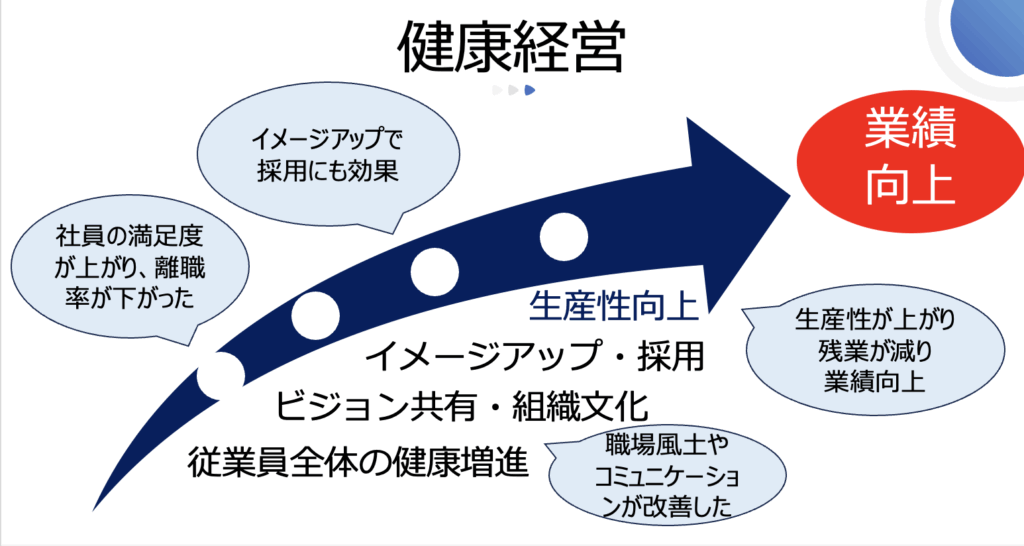
広報活動をチームで行うと、
普段は見えなかった社内の取り組みが
可視化されます。
🔹チーム広報がもたらす変化
・「その仕事、そんなに工夫してるんですね」と声をかけ合う
・ 社長の思いを発信することで「うちっていい会社だ」と再認識する
・ 部署を越えて「どうしたらもっと喜んでもらえるか」を語り合う
広報の実践を通じて、
社員同士の理解が深まり、
自然と活気のある組織に変わっていきます。
健康経営も同じです。
方法は違いますが、
「会社として社員を大切にする」という姿勢を
示すことで、組織全体の空気が変わります。
🔸ゆで卵とチーズが変えた職場風土

ある中小企業でのエピソードをご紹介します。
10年以上前、健康経営に取り組み始めた頃、
ある朝オフィスに行くと、テーブルの上に
「ゆで卵とチーズ」が置かれていました。
「どうしたの?」と聞くと、
「風邪予防にタンパク質を摂るといいと
産業医が言ってたから。仕事前に一つどうぞ」と。
その一言から会話が広がり、
次第に「朝食をパンだけで済ませていたから助かる」
「お昼に軽く食べられるのがいいね」と
いった声が交わされるようになりました。
🔹小さな習慣が広がる仕組み
そのうち、こんなことが起き始めました。
・ ママさん社員が「簡単豆腐レシピ」を紹介
・ 独身社員も手軽にできる工夫をシェア
・ 仕事以外でも健康を応援し合う雰囲気が自然に生まれる
健康施策は、一人の思いやりから始まり、
やがて社内に「心理的安全性」を育てていきます。
🔹 健康経営が文化を変える理由
健康経営の効果として「コミュニケーションが
活発になった」とよく言われます。
その背景には、共通のゴール
―― 「社員みんなが健康で働ける会社になる」 ――があるからです。
中小企業は縦割りの仕事になりがち。
「隣は何をする人ぞ」では、
周りの仕事がわからず対立しがち。
「私ばかり頑張っている」
「経営者はわかってくれない」という不満も、
共通のゴールに向かうことで和らぎます。
健康を支え合う組織は、
自然と「仕事でも助け合える組織」に変わります。
つまり、健康経営は単なる施策ではなく、
人的資本経営や心理的安全性の土台 になるのです。
🔸まとめ
健康経営を始めるのは難しいことではありません。
まずは健保組合や地域の制度を調べ、
「健康宣言」に取り組むことからスタートできます。
健康経営は、社員の健康を守るだけでなく、
・ 部署を超えた理解を深める
・ コミュニケーションを活性化する
・ お互いを尊重し合える組織文化を育てる
そんな変化を生み出します。
明日は、
「健康経営を社内に定着させる取り組み」 をご紹介します。
どうぞお楽しみに。